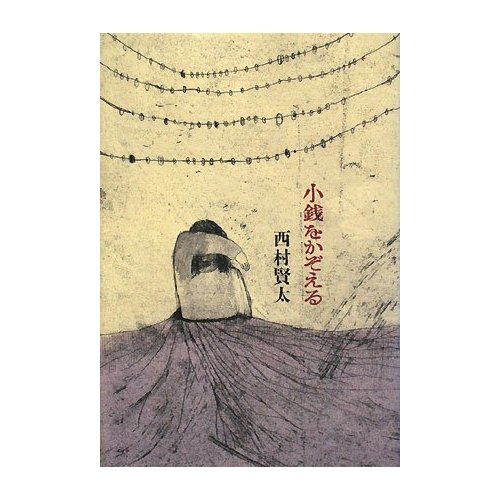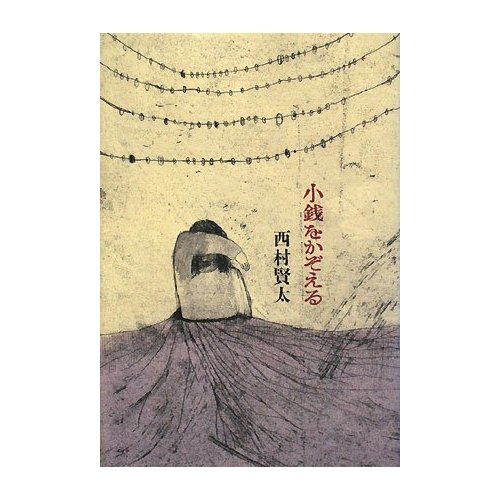西村賢太の惨めな世界
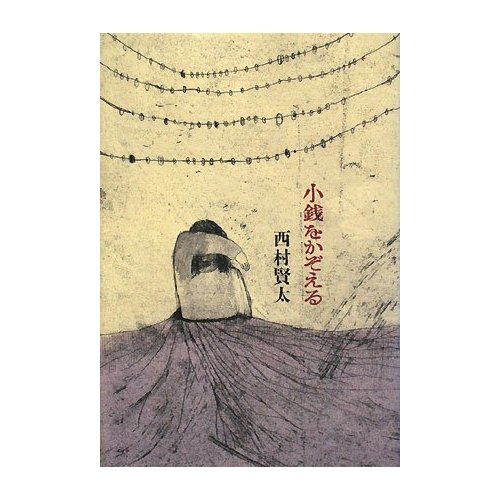
先日、西村賢太著『小銭をかぞえる』(文藝春秋)読了。芥川賞、三島由紀夫賞候補となったデヴュー作『どうで死ぬ身のひと踊り』(文藝春秋)よりまた一段成長した筆力に感服した。
西村賢太はそのうち芥川賞を取るだろう。それだけ近年ではめずらしい手応えのある小説作品であった。
といっても『どうで死ぬ身のひと踊り』も含めて、西村賢太の小説はそう簡単に誰にでも推薦できるような性質のものではない。彼の小説は基本的に私小説なのであるが、この作者自身が投影されたと思われる主人公「僕」が非常に強烈なキャラクターである。
なにしろ中卒・無職で、さらに病的な古本コレクターであり、かつ同棲している女性から古本代金を巻き上げることは日常茶飯事、それどころか女性の前歯をへし折ったりするドメスティック・バイオレンスを揮(ふる)うというのだから尋常ではない。
また西村賢太は大正期に野垂れ死にした私小説作家、藤澤清造の「没後弟子」を名乗り、藤澤清造の卒塔婆を自室に飾るほどの熱烈な藤澤マニヤであり、金沢市に存在する実在の出版社「亀鳴屋」から『藤澤清三全集全五巻+別巻二』の発行を自費出版で実現させようともくろんでいるらしい。
この『藤澤清三全集』の資金調達をめぐる同棲中の女性との惨めで貧乏臭く、いやったらしいトラブルがこの『小銭をかぞえる』という小説の中心部分をしめる。
内容はあまりに露悪的、アンチモラルであるのに対し、文体は非常に端整、言葉も良く選んで使用されている。例えば「僕」は月二回ソープランドに行くことになっているのであるが、このソープランドをそのまま書かずに「買淫」と書く。まるで大正期の作家のような古風な味わいがある。
また『小銭を数える』では『どうで死ぬ身のひと踊り』よりも小説全体の構成がよく計算されている。現実の西村賢太は作中の「僕」と同じように浮かれているわけではないのだ。小説家としての「プロ意識」を今回の『小銭を数える』から強く感じた。
一読すれば暗澹たる気分になる小説であることは確かであるが、それでもその漆黒の闇の中から確実に「西村賢太」というひとりの人間の息遣いが聞こえてくる。
生きることは誰にとってもあまりに惨めだ。しかしそれでも生きていかざるをえない。まだ死ぬわけにはいかない!どうで死ぬ身ならばその前に痛烈なひと踊りを踊ってやろうじゃないか!そのようなやがて死んでゆかなくてはいけない人間の「怒り・悔しさ」という心意気を作中の「僕」になぞらえて、見事に描写しているという点でわたしは西村賢太の小説を読者の諸氏諸兄に強く推薦するものである。
(黒猫館&黒猫館館長)